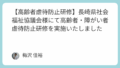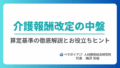1.はじめに ―「加算は取れたが、続かない」現象
「初回はうまく算定できたのに、継続運用で崩れ始めた」。
令和6年度改定後、多くの施設長から聞かれる声です。委員会は形だけで回り、記録は人によってバラバラ。LIFEは入力が滞り、フィードバックを活かせない。監査が近づくと事務方が慌てて書類をかき集める――。
この“取りっぱなし”の状況を避けるには、算定→運用→検証→改善を一気通貫で仕組み化することが欠かせません。第2回では、委員会運用・記録・監査台帳・LIFE活用を統合設計する方法を、実例を交えて解説します。
2.仕組み化の設計図 ― 要件からKPIまで一本線で結ぶ
仕組み化の要は、「要件→業務→記録→証跡→KPI」を一本の線でつなぐことです。
- 要件:条文や加算要件を“業務タスク”に翻訳する
- 業務:誰が・いつ・どこで行うのかを明確化
- 記録:定型フォーマットで証跡を残す
- 証跡:監査逆算で保管場所・責任者・更新頻度を整理
- KPI:運用結果を数値で可視化し、改善に還流する
この流れを一度設計すれば、人が入れ替わっても制度要件は守られ、成果も持続します。
3.委員会・会議体を“機能させる”方法
委員会は「回数」ではなく「機能」が問われます。形骸化を防ぐためには、アジェンダの標準化が必須です。
実践例:月次委員会のアジェンダ(45分)
- 先月のKPI振り返り(加算達成率、LIFE提出率など)
- 是正計画の進捗確認(未達成項目をどうリカバーするか)
- LIFEフィードバックをケアプランに反映(具体事例を1件共有)
- 今月の重点テーマ(虐待防止、感染症対策、記録改善など)
- 次回までのToDoを決定、RACI表に記入
効果:
- 会議時間を短縮しつつ、改善サイクルが回る
- 議事録がエビデンスとなり、監査対応にも強い
- 職員の「参加して良かった」という納得感が高まる
4.記録・様式・監査台帳を標準化する
記録は「誰が書いても同じ質」になることが理想です。
実践の工夫
- 統一様式:自由記述ではなくチェックボックス+選択肢を中心に。例文例示を併記し、書きやすくする。
- 監査逆算エビデンス台帳を用意:
- 要件 → 必要証跡 → 保存場所 → 更新頻度 → 担当者
- 例:虐待防止委員会 → 議事録・出席簿 → サーバー「委員会/虐待防止」 → 月次 → 相談員
効果:
- 証跡探しに追われることがなくなる
- 新任担当者でもすぐに業務を引き継げる
5.LIFE/ICTを“活用”する仕組み
LIFEは提出して終わりでは意味がありません。
実践例
- 入力負担軽減:介護記録ソフトと連動させ、二重入力を削減
- フィードバック活用:カンファレンスで「1件は必ずLIFEデータを根拠に議論する」ルールを導入
- 成果共有:褥瘡発生率の推移やADL維持率をグラフ化し、月次で職員と共有
効果:
- 「数字がケア改善につながった」と実感できる
- 職員のエンゲージメントが向上する
6.人材育成と定着に直結させる
仕組みを回すのは“人”です。育成を運用と結びつけることで定着率も上がります。
実践例
- 5分のマイクロラーニング動画を毎月配信し、小テストで理解度を測定
- テスト結果を人事評価と連動させ、「学び」をキャリアに反映
- 会議で改善事例を発表した職員を表彰し、モチベーションにつなげる
7.まとめ
加算は「取る」こと自体が目的ではなく、運用を仕組み化し、継続的に成果を生むことが本質です。委員会、記録、監査台帳、LIFE、教育を一気通貫で設計すれば、現場負担を増やさず経営効果を最大化できます。
8.次回予告
第3回は「令和9年度改定に負けない介護経営:2027ロードマップと投資判断チェックリスト」。
人材確保、ICT投資、地域連携の優先度をどう決めるか、中期計画づくりの視点を解説します。