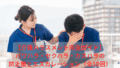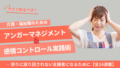皆さま こんにちは ベラガイア17の梅沢佳裕です。
今回の研修は、介護老人福祉施設 豊玉南しあわせの里様から研修のご依頼を頂き、講師を務めさせて頂きました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.研修概要
■テーマ:三大ハラスメント防止研修―パワハラ・セクハラ・カスハラ対処の基本と防止策
■開催日時:2025年8月13日(水)17:10~18:40(集合研修)
■研修場所:介護老人福祉施設 豊玉南しあわせの里 様

【研修プログラム】
- はじめに:介護現場における“ハラスメント”とは?
→ なぜ今、介護現場での対策が求められているのかを解説 - 講義①三大ハラスメントの基礎知識(パワハラ・セクハラ・カスハラ)
→ 定義・類型・具体例・対応の原則 - ワーク①これはハラスメント? ~事例から考える~
→ 架空事例から「該当する?しない?」をグループで検討 - 講義②介護現場におけるハラスメントの対処法
→ 現場レベルでの未然防止・初期対応・チーム連携の工夫 - ワーク②グレーゾーン対応を考える
→ 小さな取り組み・気づき・声かけなどをペアで対話 - 講義③:介護現場におけるハラスメントの防止策
→職場全体で三大ハラスメントを防ぐための具体策を共有する
7.まとめ・振り返り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.研修の様子
本研修は、介護現場での「三大ハラスメント」―パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント―を正しく理解し、予防と適切な対応を身につけることを目的として実施しました。介護事業所の職員、管理者、相談員など、幅広い立場の方々を対象に、具体的な事例や最新の制度・法令に基づきながら進行しました。
研修は大きく3つの講義と2つのワークで構成され、冒頭ではハラスメントの定義や種類、介護現場での特徴を共有しました。続いて、各ハラスメントの実態や法的背景、被害防止のための組織的取り組みについて解説しました。特に、カスタマーハラスメントに関しては、厚生労働省指針やガイドラインに沿って、利用者や家族からの不適切行為への対応手順を整理しました。
また、研修中盤にはグループワークを行い、参加者同士で事例をもとに対応策を検討・共有しました。実際の現場を想定したディスカッションを通じて、法令遵守だけでなく、利用者や家族との関係性を維持しながら職員を守る方法について学びました。
最後に、研修全体のまとめとして、各参加者が「自分が明日から実践できる取り組み」を言葉にして共有しました。これにより、研修で得た知識を日常業務に直結させ、職場全体でハラスメント防止の意識を高めることを目指しました。ご参加くださったスタッフの皆さま、ありがとうございました。
【研修にご参加されたスタッフ様へ】
■ワークについての解説
ワーク①の解説
「ワーク事例の解説― ハラスメントかどうか考える視点」
事例①(パワハラの可能性)
人格を否定する言動(そんなこともできないの?)」や、繰り返しの叱責によって心理的負荷を与える場合、職場におけるパワハラに該当する可能性があります。相手が萎縮し、心身不調に至っていれば要注意です。
事例②(セクハラの可能性)
外見に関する発言が、相手に不快感や苦痛を与えている場合、セクシャルハラスメントと判断されますが、利用者に認知症によるBPSDがある場合は、ハラスメントではなく認知症ケアとして対応策を検討する必要があります。※厚労省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」令和4年
事例③(カスハラの可能性)
サービス提供に対して威圧的・理不尽な言動が続く場合、カスタマーハラスメントに該当します。職員が委縮したり交代を強要されたりする状況では、組織的対応が必要です。
ワーク②の解説
事例①:中堅職員による「指導」という名の叱責
見えにくいパワハラの芽は、組織で気づく仕組みづくりから。
- 「指導」と「叱責」の違いを、共通認識として職場で共有しておく
→ 指導の“やり方”まで含めて、日ごろから声かけやOJT指導に関する方針を明文化する - 「誰かがつらい思いをしていないか」周囲が声をかけ合える風土づくり
→ 定期的な面談や振り返りの場で、遠慮なく話せる仕組みを!
事例②:利用者からの接触と困惑
認知症ケアとハラスメントの“狭間”をどう捉えるかは、個人任せにしない。
- 「利用者だから仕方ない」と済ませず、困ったときはすぐ共有できる文化をつくる
→ 日々の記録や申し送りで、“どこまでが許容範囲か”をチームで確認 - 本人の行動背景(BPSDなど)も含めて、ケアチームで対応策を検討する習慣を
→ 職員が“耐える”形にならないよう、配置や関わり方を工夫する
事例③:家族からの怒声・詰問・過度な要求
カスハラは“施設全体で守るべき”問題。前もっての準備が鍵に。
- 苦情とカスハラの線引きを共有し、マニュアルや対応ルールをチームで整備
→ 記録・報告の徹底、対応方針の統一などで、現場任せを防ぐ - 新人や若手が標的になりやすい傾向があるため、対応時は複数人で行動
→ 一人で抱えさせず、リーダーや管理者が“前に出る”姿勢が重要