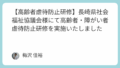〜介護・福祉職のための感情コントロール実践術〜
介護・福祉の現場で働く皆さん、こんにちは。
前回は「呼吸法と身体の使い方」による感情コントロールをご紹介しました。
今回は、より実践的に「言葉の選び方」に注目します。
日々のケア業務では、利用者やご家族、同僚との会話のなかで「つい感情的になってしまった」「思っていない強い言葉を口にしてしまった」と後悔することはありませんか?
実は、怒りを和らげるには「何を伝えるか」よりも「どう伝えるか」が大きなカギを握ります。
ここでは、現場で活かせる具体的な言葉の選び方と、その効果的な使い方をご紹介します。
1.感情をぶつけずに事実を伝える「I(アイ)メッセージ」
怒りにまかせた言葉の多くは「あなたが悪い」というYou(ユー)メッセージになりがちです。
例:
- 「あなたが遅いから困るんです!」
- 「どうしてちゃんとやってくれないんですか!」
これでは相手を責める印象が強く、関係性が悪化する原因となります。
一方で、I(アイ)メッセージを使うと、感情をぶつけずに事実と自分の気持ちを伝えられます。
例:
- 「予定より遅れると、私も次の対応に影響が出てしまいます」
- 「急に変わると、私も準備が間に合わずに困ってしまいます」
ポイントは、自分の感情や困りごとを主語にすること。
これだけで相手の受け取り方は大きく変わり、対話が前向きになります。
2.語尾やトーンの工夫で印象を変える
同じ言葉でも、語尾や声のトーンで相手に与える印象はまったく違います。
怒りが強いときほど、無意識に語尾がきつくなりがちです。
例:
- 「早くしてください!」 → 怒り・命令に聞こえる
- 「できれば早めにお願いできますか?」 → 協力依頼に聞こえる
また、トーンも大切です。
声を少し落ち着けて話すだけで、相手は「冷静に話している」と感じ、受け止めやすくなります。
介護・看護職は「声かけ」が仕事の一部。だからこそ、語尾や声の高さを意識するだけで、感情のぶつかりを防げるのです。
3.「でも」「しかし」を避けるリフレーミング
会話の中で「でも」「しかし」を多用すると、相手の意見を否定している印象を与えます。
否定から入ると相手は防御的になり、怒りがぶつかりやすくなります。
そこで活用できるのが”リフレーミング(言い換え)”です。
例:
- 「でも、難しいですね」 → 「そうですね、その一方でこういう方法もあります」
- 「しかし、できません」 → 「現状では難しいのですが、こうなら可能です」
否定の接続詞を避け、肯定+提案の流れに変えることで、会話が建設的になります。
4.介護・看護の場面別フレーズ集
最後に、実際の介護・看護現場で使えるフレーズ例を紹介します。
利用者対応
- 「早くして!」と言われた時
→ 「お待たせしてしまいすみません、すぐに伺いますね」 - 拒否が強い場面
→ 「無理にではなく、○○さんのペースでできるところから一緒にやりましょう」
ご家族対応
- 厳しいクレームを受けた時
→ 「ご不安にさせてしまったことを申し訳なく思います。どうすれば安心いただけるか一緒に考えさせてください」
職場内(同僚・後輩)
- 業務が滞った時
→ 「手が回らなくて困っているんだ、少しだけ協力してもらえますか?」 - 意見が対立した時
→ 「なるほど、そういう見方もありますね。そのうえで、私の考えはこうです」
こうしたフレーズをストックしておくと、とっさの場面でも感情的にならずに対応できます。
まとめ|言葉の選び方が感情を変える
怒りを和らげるには、感情を抑え込むのではなく、言葉の伝え方を工夫することが効果的です。
- Iメッセージで感情をぶつけずに事実を伝える
- 語尾やトーンで印象をやわらげる
- リフレーミングで会話を前向きに変える
- フレーズ集を日常に活かす
これらはすべて、介護・看護職が現場で即実践できる技術です。
次回は、「怒りを未然に防ぐ“環境づくり”」についてご紹介します。
職場全体で感情の安定を支える工夫を一緒に考えていきましょう。