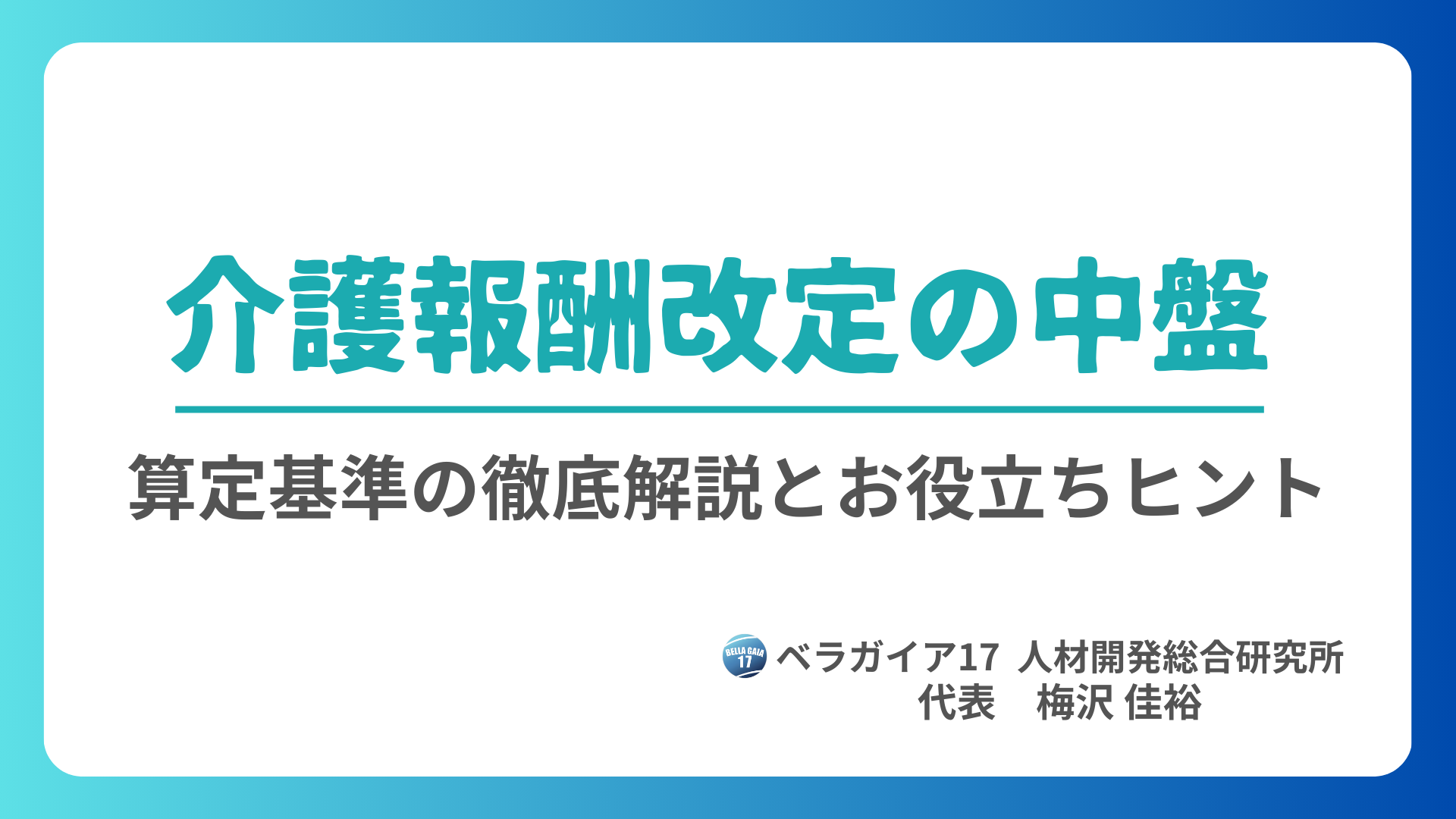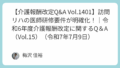2024年度の介護報酬改定で、すべての介護サービス事業所に業務継続計画(BCP)の策定と訓練の実施が義務化されました。
しかし現場ではこんな声がよく聞かれます。
• 「BCPは作ったけど、現場職員は知らない」
• 「訓練って何をすればいいのか分からない」
• 「実際に役立つ計画になっているか不安」
この連載では、自然災害に備えた‶実効性あるBCP”をどう訓練・研修で育てるか″を3回にわたって解説します。
第1回は、「なぜBCP訓練が必要なのか?」を分かりやすくお伝えします。
机上訓練とは? ― 現場でできる‶最初の一歩″
BCP訓練には主に以下の2種類があります。
• 実動訓練: 実際に体を動かして避難や連絡の練習をする
• 机上訓練(シミュレーション訓練): 想定シナリオに沿って対応を検証する
介護施設では、安全面や業務の負担からまずは「机上訓練」から始めるのが現実的です。
たとえば、以下のような場面を想定します。
地震発生により、エレベーターが停止。2階の車いす利用者5名をどうやって1階に避難させる?
こうした「もしも」に対して職員が話し合い、実行可能かどうか、何が不足しているかを確認するのが机上訓練の目的です。
実例:訓練で発覚した“想定の甘さ”
あるデイサービスでは、BCPにこう記載していました。
「地域の指定避難所に徒歩で避難する」
ところが訓練で判明したのは…
• 車いす利用者が5名、介助者が3名ではマンパワーが不足
• 避難所までの歩道に段差が多く、通行困難
• 雨天時の代替手段が用意されていない
•
この結果、以下のようにBCPを見直すことになりました。
✅ 施設内避難(1階多目的室)への切り替え
✅ 地域包括支援センターとの情報連携ルートを強化
✅ 送迎車を活用した「避難用車両マニュアル」を作成
BCPの実効性は、訓練を通して初めて見えてきます。
BCP=非常時の‶暮らしの継続計画″
BCPという言葉は難しく感じがちですが、自然災害BCPはあくまで「日常を守る」ための計画です。
災害時に必要なのは、以下のような当たり前の暮らしをどう維持するかという視点です。
• 停電時の食事提供や排泄対応
• 通信手段が切れたときの家族への連絡
• スタッフが出勤できない場合の最低限の人員確保
•
さらに最近では、「パーソナルBCP(職員ごとの行動計画)」を導入する施設も増えています。
各職員が「自分の家族・通勤手段・出勤可否」を整理し、災害時の動き方を明確にするのが目的です。
‶BCPを現場に根づかせる″3つの工夫
BCPが形骸化する理由の多くは、現場とBCP担当者の意識ギャップです。
これを埋めるために、以下の工夫が効果的です。
✅全員参加の机上訓練
→ 介護・看護・調理・事務など多職種で意見を出し合う
→ 「自分はこの場面でどう動くか?」を考えることで行動意識が育つ
✅ カードやシートを使った“ゲーム形式研修”
→ たとえば「災害時の役割分担カード」を配布し、模擬状況をチームで検討
→ 新人・非常勤職員の参加意識も高まる
✅ 訓練後の“ふりかえりミーティング”
→ 「気づいたこと」「うまくいかなかった点」を話し合い、BCP改訂につなげる
まとめ:BCPは「動かしてこそ意味がある」
BCPは作って終わりではなく、「実際に動かして、見直して、現場で使える状態にする」ことが真の目的です。
訓練と研修を通して、BCPは“絵に描いた餅”から“動ける備え”へと進化します。