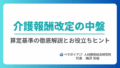皆さま、こんにちは。ベラガイア17人材開発総合研究所の梅沢佳裕です。
生活相談員の連載ブログも今回がいよいよラスト!
さっそく相談員の多角的な視点から、解説していくことにいたしましょう!
介護施設で働く生活相談員には、日々さまざまな判断と対応が求められます。
誰のために、何のために、どの立場に立って行動するのか――。
そこで重要になるのが、**多角的な視点=「5つの視点」**です。
本最終回では、相談援助の実践を支える「利用者・家族・職員・地域・経営」という5つの視点について、具体例と共にわかりやすく解説します。
この視点を意識することが、相談員としての“ぶれない軸”となります。
1.利用者の視点:その人らしさに寄り添う
相談援助の出発点は、やはり利用者本人の思いや尊厳にあります。
「食事をゆっくり食べたい」「ひとりの時間がほしい」など、些細な願いに耳を傾けることが、生活支援の質を高めます。
🔹たとえば…
「職員の誘導で嫌々レクに参加しているAさん」
→レクよりも「静かに過ごす時間」が本人にとっての大切な日課かもしれません。
相談員は、本人の希望を代弁し、チームに届けるソーシャルワーカーとしての役割を果たします。
2.家族の視点:不安と希望の“揺れ”を受けとめる
家族は、介護する立場でもあり、悩む存在でもあります。
「本当にこれでよかったのか」「もっとできたのではないか」――その揺れる気持ちに、相談員は共感と情報提供で応えます。
🔹たとえば…
「急な入所で混乱している家族」
→「ご不安な中で、よくご決断されましたね」と、プロセスを肯定しつつ丁寧に説明を行う。
相談員に求められるのは、“正しい答え”ではなく、寄り添う対話です。
3.職員の視点:現場との温度差を埋める調整力
介護・看護・リハなどの現場スタッフが日々感じることを、制度やご家族の意向とすり合わせていくのも相談員の仕事です。
🔹たとえば…
「もっと入浴を増やして」と要望する家族に対し、介護職は「人手が足りず難しい」と苦悩している。
→相談員は、現場の声を代弁しつつ、「家族の思い」と「現実の制約」をすり合わせる調整を行います。
ここでは″メゾ・ソーシャルワークの視点(中間支援)”が活きてきます。
4.地域の視点:施設を“開いた存在”に
施設は、地域から利用者を迎え入れ、また地域に向けて支援を広げていく場所でもあります。
相談員は、その「つなぎ役」として外部機関と関係を築いていきます。
🔹たとえば…
地域包括支援センター、行政、医療機関、民生委員などと定期的に連携を取ることで、支援の幅が広がります。
これは″マクロ・ソーシャルワーク(社会資源との連携)”の視点です。
5.経営の視点:施設全体を支える一員として
相談員の対応ひとつが、施設の信頼や収支に影響することもあります。
苦情対応、事故報告、加算運用――一見“現場支援”とは別に見える業務も、経営の視点で考えると、非常に重要です。
🔹たとえば…
相談員が誠実に対応した結果、ご家族からの信頼が高まり、新規入所の紹介につながるケースもあります。
相談員は、現場と経営をつなぐ″広い視野”を持つ存在でもあるのです。
■まとめ:多角的な視点こそ、相談員の力
生活相談員の仕事は、マニュアル通りにいかない場面の連続です。
そんな中でも、「この行動は誰の視点から見るとどう見えるか?」を自問することが、質の高い支援へとつながります。
- 利用者の思いに寄り添い
- 家族の不安をくみ取り
- 職員の声をすくい上げ
- 地域とつながり
- 経営を意識して動く
これら5つの視点を行き来できる力こそ、生活相談員の専門性=実践的ソーシャルワークの力です。
▶最終回に寄せて
この5回の連載を通して、生活相談員という仕事の奥深さと、その専門性を少しでも伝えられていたら幸いです。
あなたの「つなぐ力」が、誰かの安心につながる。
その手応えを大切に、今日も現場で、あなたらしい支援を続けてください